50代でFIREめざしているときちです。
FIREの先には老後生活が待ち受けていますが、老後生活を考える上で気になるのが健康問題。
年を取れば体もガタがきますので、若いうちにはお世話にならなかった病院へ行く機会も増えるのは必然です。
そうすると、医療費はどの位かかるのか、介護費用はどうなのかなど、出口戦略と同時に将来の医療費などに対する備えを懸念する方も多いと思います。
ときちは、本業で健康保険関連も取り扱っていますので、日常的に健康保険関連の相談にものってきた経験があります。
医療費の備えが必要なのかを考える前に、健康保険のざっくりとした制度を再確認し、将来の医療費について考えてみます。
医療保険制度の種類
健康保険制度の概要は、過去記事にも投稿しました。
今回は、FIRE後、又は老後に加入する健康保険についてまとめようと思いますが、その前に健康保険制度の概要を簡単にまとめます。
健康保険の種類は次の通りです。
- 社会保険 ・・・・ 協会けんぽや健保組合 働いている人が会社を通じて加入
- 国保組合 ・・・・ 業種によって国保組合を所有 社会保険とほぼ同じ
- 公営国保 ・・・・ 市区町村で加入する健康保険 事業主・無職などが加入
- 後期高齢者 ・・・ 後期高齢者医療制度 75歳以上の人は全てこの健保
以上ですが、細かに分類すると、公務員が加入する共済保険もありますが、これは社会保険とほぼ同じなので割愛しました。
ざっくりいえば、雇われていれば社会保険(又は国保組合)の健康保険で、無職の方や個人事業所の事業主、フリーランス、専業主婦など、社会保険に該当しない人は公営国保の加入となります。
ですので、仕事をやめてFIREした時や、老後は公営国保へ加入します。
ただし、75歳に到達すると、例え雇われていても後期高齢者医療制度へ移行します。
医療費の自己負担はいくら?
以前は加入する健康保険制度によって自己負担割合が異なっていましたが、いまは原則本人3割自己負担となります。
後期高齢者医療制度は、負担割合が異なりますが、今回は割愛させて頂きます。
従いまして、公営国保に加入しても、現役時代同様に自己負担割合は3割となります。
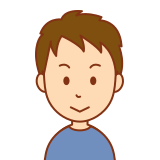
医療費も高くなってきているようなので、大病すると飛んでもない金額を払うことになるの?
医療分野の進歩は、病気の克服・長寿への道を切り開きますので、人類にとって喜ばしい進歩ではありますが、同時に高度化していますので、新しい技術や新薬は莫大な費用がかかります。
ゾルゲンスマという脊髄性筋萎縮症の薬剤は、1億円をゆうに超えますので、そうすると自己負担が3000万円以上となるの??と不安になります。
そこで自己負担の上限を設けているのが、今年の国会でも話題になりました、高額療養費制度です。
高額療養費制度は、収入に応じて自己負担の上限が設けられています。
70歳未満の方の区分
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当(※2) |
|---|---|---|
| ① 区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) (報酬月額81万円以上の方) | 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% | 140,100円 |
| ② 区分イ(標準報酬月額53万〜79万円の方) (報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方) | 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ③ 区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円の方) (報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方) | 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% | 44,400円 |
| ④ 区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) | 57,600円 | 44,400円 |
| ⑤ 区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
例えば、区分ウの標準報酬月額28万~50万の場合、80,100円に医療費総額から267,000円を差し引いた金額の1%となります。ですので、よほど高度で高額な治療を受けなければ、月10万円弱位の負担額になると考えてください。
65歳から75歳は、前期高齢者となり、加入している医療制度とは別に前期高齢者医療助成対象となりますが、原則3割自己負担となり、所得が低い方のみ2割負担となります。
前期高齢者のうち、70歳~75歳に関しては、高額療養費制度が若干緩和されます。
75歳以上になりますと、後期高齢者医療制度になりますので、こちらも高額療養費制度は異なります。
後期高齢者医療制度は、所得に応じてそもそも負担割合が異なり、その割合に応じた高額療養費制度が設定されています。
| 負担 割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) | |
|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得Ⅲ課税所得690万円以上 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%多数回:140,100円 | |
| 現役並み所得Ⅱ課税所得380万円以上 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%多数回:93,000円 | ||
| 現役並み所得Ⅰ課税所得145万円以上 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%多数回:44,400円 | ||
| 負担 割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|---|
| 2割 | 一般Ⅱ | 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%または 18,000円のいずれか低い方【令和7年10月1日以降は一律18,000円】(年間上限144,000円) | 57,600円多数回:44,400円 |
| 1割 | 一般Ⅰ | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円多数回:44,400円 |
| 区分Ⅱ住民税非課税等 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区分Ⅰ住民税非課税等 | 8,000円 | 15,000円 |
従って、医療費に対して一定の備えは必要かもしれませんが、高額療養費制度はじめ、多額の負担にならないような制度設計となっていますので、過度な不安は不要です。
国民健康保険の注意点
社会保険だと、病気などで仕事を休んだときに傷病見舞金が支給されますが、国民健康保険だと傷病見舞金制度がありませんので、例え収入があっても何も保障はありません。
入院時の所得補償が欲しい場合は、民間保険などを活用するしかありません。
あと、過去記事でも記載しましたが、保険料の算定方法の1つに所得割があり、この所得は前年度所得が算定対象となりますので、退職後には結構高い金額の保険料となります。
この辺りは過去記事をご参照ください。
あとは、子どもの医療費助成や難病、特定疾病、障害者などの医療費助成や、生活保護受給世帯の給付は異なったりしますが、この辺は割愛します。
健康保険診療外の負担
健康保険診療内の負担に関しては、自己負担割合と高額療養費制度でカバーされますが、実はそれ以外にも費用はかかります。
健康保険診療内とは、健康保険でカバーされる診療のことで、健康保険では保障されないものもいくつかあります。
特に注意が必要なのは入院時で、以下のものが実費請求されます。
- 差額ベッド代
- 食事代
- リネン代
などです。
特に差額ベッド代は個室にはいると結構な金額になり、その金額は医療機関で設定できるので、金額はまちまちです。
入院するとき、経済的に不安であれば、事前に「大部屋希望」と強く要望し、「個室しか空きがない」と言われたら、「金がない」と交渉すれば、大部屋を案内されるか、金額の調整をしてくれることもあるかもしれません。
また、自己負担でいうと歯科も注意です。
インプラントはじめ、健康保険診療外の治療もあり、事前に説明はありますが、結構自己負担の治療があるので、注意して聞きましょう。
あと産科の扱いや健康診査などの留意もありますが、今回のテーマとは異なりますので、こちらも割愛します。
まとめ
今回は、国民健康保険の話を中心にまとめました。
FIRE後、老後に加入する健康保険は、大半の方が国民健康保険となりますので、出口戦略の設定にあたり、参考にしてもらえれば幸いです。
ちなみに、健康保険の選択肢としては、退職直後であれば社会保険の任意継続も利用できますし、独立開業して法人化すれば社会保険の適用、どこかでまた働くようになれば社会保険適用となりますので、ご留意ください。
健康が一番ですが、加齢とともに病気は避けて通れません。
病気に出来る限りならないよう、健康対策も必要ですね。
ときち



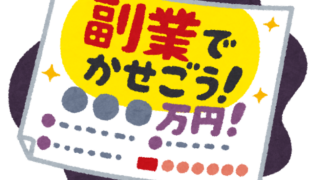




コメント