50代でFIREめざしているときちです。
ときちは、FIREに向けた資産形成を株式投資中心におこなっていますが、投資信託と個別株の両方で運用しています。
基本的には、NISAなどで投資信託メイン(特にインデックス)の戦略ですが、それだけだと正直つまらないので、個別株や債券にも投資しています。
今回は、個別株で銘柄を選定する際の指標の「1つ」となる連続増配や高配当などの話しを中心にまとめます。
なお、過去記事でも記載しましたとおり、株式投資は余剰資金で行うこと、リスクはゼロではないので自己責任でおこなうこと、そして、今回具体的な銘柄がでてきますがその銘柄の購入を斡旋するものではないこと、などはご留意ください。
なお、今回登場する用語については、過去記事もぜひご参照ください。
50代以上は投資信託から高配当銘柄や債券などへ移行?
まずはじめに、何で今回この記事を書くに至ったかの理由の1つである一般的に言われていることをご紹介します。
ときちのような初心者が株式投資する場合、投資のプロが運用する投資信託で資産形成するのが妥当だと思いますが、50代になり老後・年金生活が近づいてくると、よりリスクの低く、資産の取り崩しが比較的容易でもある個別株の高配当銘柄や、リスクが極めて低い債券への移行がすすめられています。
インデックスファンドで有名なオルカンやS&P500などは、運用利回りが10%前後と紹介されていることもあり、高配当といわれる3~4%と比較すると大きな差違がありますが、インデックスファンドでいわれる運用利回りは長期保有が前提となりますので、長いスパンの中で結果として期待できる運用利回りとなります。
何が言いたいかというと、50代を過ぎても株式投資は中長期運用が基本となりますが、若い人と比べると、20年、30年スパンでの投資は現実的ではありませんので、万が一、暴落時にさしかかってしまうと、想定していた運用利回りが期待できなくなります。
高配当銘柄でも暴落がきたら同じようなことにはなりますが、個別企業単位となるのと、株価は下がっても経済が崩壊しない限り配当金は一定期待できることから、高配当銘柄への移行がすすめられているのでしょうね。
ときちの場合、単純に個別銘柄の売買が面白くて手をだしているだけですが、いずれは投資信託から高配当へ一定切り替えたいとも思っています。
ただ、あくまで一般論であって、結局は判断は自己責任となります。しつこくてすみませんが、大事なことですので、改めて記載させていただきました。
高配当銘柄を中心とした銘柄選定
あくまで、ときちの戦略・考え方をご紹介します。
個別株への投資であっても、基本は長期保有を考えてます(一部、遊びで短期保有を想定した銘柄もありますが、あくまで例外です)。
個別株で利益を確保する場合、株価の差益で考えるキャピタルゲインと、配当金を期待したインカムゲインとありますが、ときちはインカムゲイン目的で個別株を購入していますので、長期保有は必然となります。
インカムゲインを考えた場合、配当金が多いに越したことありません。
そこで指標の一つとなるのが高配当銘柄です。
一般的に、高配当とは3~4%と言われていますが、ときちも3%台後半から高配当と考えて選ぶようにしています。
しかし、高配当といっても注意が必要です。
企業の業績が悪くて株価が下がり、結果として配当利回りが高くなっているケースや、意図的に高配当にして株式操作(表現が適切ではないかもしれません、すみません)するケースなどもありますので、高配当だからといって飛びつくのは危険です。
ときちのような初心者の場合、個別株の銘柄選定は、高配当だけでなく誰もが聞いたことのある有名な大企業中心に購入するのが無難です。
大手企業でも、過去に東京電力株が暴落(東日本大震災)した例もありますので、過信はできませんが、それでもリスクは軽減できます。
業績分析と予測が本則ですが、そこまでできませんし、結局、「絶対」はありません。
こう説明すると「やっぱり株式投資はギャンブル性があって怖い」となるかもしれませんが、分散投資すれば一定リスクを軽減できます。
1社に全財産を委ねるようなことはせず、複数の優良企業へ分散して投資。業種もわけた方がいいですね。
累進配当や配当性向で将来の配当金予測
現在の配当金は配当利回りで判断できますが、将来にわたって配当金が約束された訳ではありません。
配当金はあくまで利益の分配ですので、利益がでない、または減益の場合は、配当金が減額されるかもしれません。
そこで、将来の配当金を一定予測する指標として、配当性向と累進配当でみれます。
配当性向は、利益の配当金分配率を示すもので、企業によっては配当性向の向上を示唆していることもあります。配当性向が高い企業や配当性向の指標を示している企業は、株主還元を重要視している傾向にあります。
配当性向が高い企業が優良、とはいいませんが、株主にとってみると、一定の評価ができるのではないでしょうか。
また、累進配当を明言している企業であれば、将来にわたり配当金を引き上げることを約束していることになります。
累進配当宣言していなくても、増配を繰り返していれば、将来の配当金に一定の期待もできますので、累進配当同様にポジティブな評価ができるといえます。
ちなみに、2025年10月1日現在における連続増配企業は以下のとおりですので、ご参考までに(ダイヤモンド社から転用)。
※下記の企業の株購入を推奨する意図で紹介している訳ではありません。
| ■連続増配期間が長い株ランキング ベスト20(2025年10月1日時点) | |||||
| 連続増配 年数 | 増配率 増配開始来 | 増配率 (直近3年) | 配当利回り (予想) | 最低投資額 | |
| 1位 | 花王(東P・4452) | ||||
| 35年 | 21.4倍 | 1.05倍 | 2.39% | 64万4000円 | |
| 2位 | SPK(東P・7466) | ||||
| 27年 | 8.0倍 | 1.50倍 | 2.99% | 22万7100円 | |
| 3位 | 三菱HCキャピタル(東P・8593) | ||||
| 26年 | 50.0倍 | 1.42倍 | 3.77% | 11万9250円 | |
| 4位 | 小林製薬(東P・4967) | ||||
| 25年 | 20.4倍 | 1.22倍 | 1.95% | 53万900円 | |
| 5位 | ユー・エス・エス(東P、名P・4732) | ||||
| 25年 | 260.4倍 | 1.31倍 | 2.97% | 16万9600円 | |
| 5位 | リコーリース(東P・8566) | ||||
| 25年 | 14.4倍 | 1.50倍 | 3.25% | 56万9000円 | |
| 7位 | ユニ・チャーム(東P・8113) | ||||
| 23年 | 19.7倍 | 1.21倍 | 1.89% | 9万5050円 | |
| 8位 | リンナイ(東P、名P・5947) | ||||
| 23年 | 13.3倍 | 1.71倍 | 2.88% | 34万6600円 | |
| 8位 | サンドラッグ(東P・9989) | ||||
| 23年 | 34.6倍 | 1.83倍 | 3.08% | 42万4700円 | |
ときちが保有しているのは、ユーエスエスだけでした(涙
個別株はキャピタルゲインも期待できる
言っていることが矛盾するかもしれませんが、個別株はキャピタルゲインも期待できるのが美味しいところです。
繰り返しになりますが、株式投資にギャンブル性は求めていませんし、求めるのは危険ですので長期保有・インカムゲイン狙いが原則の戦略としておこなっていますが、それでも株価が急騰した際にはキャピタルゲインを狙ってもかまいません。
ときちも、個別株を分散しすぎて管理が不安になり、整理目的で複数の銘柄を手放しましたが、今年だけで売買益は60万円弱となります。
実は、配当金収入より売買益の方が数倍も儲かっているのですが、これに味を占めてキャピタルゲイン狙いのディトレーダーになっては、知識もありませんし時間も確保できませんので、絶対に痛い目にあいます。
ですので、基本戦略はインカムゲイン狙いの長期保有であり、その方針は絶対に崩す気はありませんが、たまには売ってもいいんじゃないかなぁ・・と思っています(汗
まとめ
今回は、個別株の銘柄選定で、高配当株を選ぶ際の留意点についてまとめました。
あくまで、ときちの視点ですので、参考程度にとどめてください。
あと、繰り返しになりますが、前掲の企業は購入をすすめている訳ではなく、現段階におけるランキングを紹介しただけですので、誤解のないようにしてください。
株式投資をギャンブル化させないためには、堅実な投資方針が必要です。
そのためにも、長期保有が原則となり、株価が下がっても狼狽売りしないホールド力も必要となります。
株価で一喜一憂しないためにも、購入後は株価チェックしないのも手らしいですが、ときちはついつい見てしまいます。
50代以降の方で投資信託メインの方は、高配当株へ切り替えることも一つの手法論ですので、今回の記事を参考にして頂ければ幸いです。
また、個別株の購入を検討している方も、参考にしてみてください。
ときち



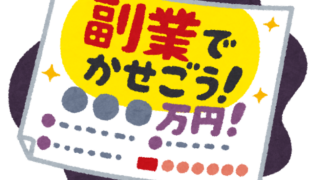






コメント