50代でFIREめざしているときちです。
読者の方は、FIREに興味がある、またはFIREを考えている方、そして定年退職間近な方などが中心かなと思っています。
FIREするにしても、定年退職後の老後生活を考えるにしても、現在働いている職場を「退職」するということは共通で、退職すると「え?何これ?」といった、想定していなかった負担が請求されてきます。
ときちは、仕事柄、こうした関連の相談にも対応してきましたが、以外と皆さん知らない制度が多いようですので、今回は退職後に気をつけることを中心にまとめます。
なお、FIREを考えるにあたって出口戦略は必要ですが、それは別の記事にまとめていますので、そちらをご参照ください。
それでは早速はじめていきましょう。
住民税の罠
私たちは、多様な税金を日々支払っていますが、給料から天引きされている税金でいうと、所得税と住民税が該当します。
所得税はその名の通り「所得に応じた税金」ですので、給与収入の方は稼いだ給料の額面によって、所得税が確定します。
労働者の場合、確定申告で税額計算するのではなく、毎月、おおよその所得税を税務当局が作成した早見表で計算する「源泉税方式」ですので、自分自身が意識することなく税金が給料から差し引かれ、年末に最終調整されます。これが年末調整です。
したがいまして、所得税は「所得」が発生しなければ税金も発生しませんので、退職後に何らかの収入がなければ、現役時代のように所得税を支払う義務も発生しません。
問題は住民税です。
住民税も年間所得に応じて計算されますので、税額計算の仕組みそのものは所得税と類似していますが、問題は対象となる所得の期間です。
所得税が当年課税なことに対して、住民税は「前年度所得」が課税対象となります。
即ち、2025年に支払う住民税は2024年の所得が課税対象となります。
例えば2025年4月に退職した場合を考えます。
住民税は5月に支払い額が通知され、6月より納付することになりますが、2025年4月に退職していると、2025年6月には仕事を辞めているにもかかわらず、2024年の所得に応じた住民税が請求されるので、現役時代並みの住民税を支払う義務が生じます。
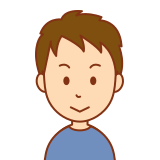
収入がないのに住民税払うの?
そういうことになります。
しかも、住民税の納付方法は普通徴収と特別徴収があり、普通徴収は個人が直接役所へ支払う方法、特別徴収は雇い主が給料から住民税を天引きし、まとめて支払う方法ですが、ほとんどの方が特別徴収となっているはずですので、住民税額を意識していない可能性が非常に高いのではないでしょうか。
なので、収入がない中での住民税負担もそうですが、そもそも「住民税ってこんなに高かったの?」と思うかもしれません。
なお、住民税は、所得割と均等割があり、所得割には総所得から控除を差し引いた金額に10%を乗じることになります。
控除の内容等は、まとめると膨大な量になりますので割愛しますが、所得計算を知っている方であれば、概ね所得税の控除内容と同じような感じです。
ちなみに、「ふるさと納税」を利用していると、その分、税額がおさえられます。正確には、本来払うべき税額を「ふるさと納税」として事前に支払っていますから、支払う税額が安くなる訳ではありません。
キャンプ好きの方は、ふるさと納税を利用して、キャンプギアを購入してみては?
なので、退職後に住民税が請求されますので、退職する前に住民税額を確認し、1年分の住民税を別途用意することをおすすめします。
健康保険料 ~どこの健康保険にはいるか~
在職中は社会保険に加入していますので、協会けんぽ(大企業だと組合健保)と厚生年金に加入しています。
公務員だと共済保険ですね。
まだ他の選択肢もあるのですが、この辺りはまとめると長くなりますので、割愛します。
話しを戻して・・・・現職の頃は社会保険加入でしたので、健康保険は会社で加入(正確な表現ではありませんが)し、保険料も会社が半分負担してくれています。
社会保険は給料に応じて保険料が決まりますが、この辺も割愛。
退職すると、社会保険は資格喪失となりますので、どの健康保険に加入するかということになります。
退職後、仕事をしないのであれば、本来、市区町村(いまは都道府県が主体)が運営する公営国保に加入することになりますが、公営国保の保険料計算にまた罠があります。
公営国保の保険料算定は所得割や均等割など、自治体によって詳細は異なりますが、とにかく所得割は間違いなくあります。
その所得割の対象となる期間が、前年度です。
そう、住民税の時と同じですね。
現在(2025年)の国保料上限額が年間92万円ですので、月平均8万円弱となります。
結構やばくないですか(汗
あくまでも上限ですから、どのくらい稼いでいたかによって金額は異なりますし、自治体によって計算方法もかわりますので、目安が記載できずすみません。
ちなみに、結婚されている方で配偶者がフルタイム労働者の場合、配偶者の扶養家族に加入すれば保険料は発生しませんが、もし退職後に雇用保険(失業保険)の給付を考えているようでしたら、基本的に扶養家族になれません。おかしな制度ですね。
退職後の健康保険は公営国保加入が原則と言いましたが、もう1つ方法があります。
それは「任意継続」です。
社会保険を「任意」で「継続」できる制度ですので、本人が望めば利用できるよ、といった制度となります。
利用出来る期間は2年で、保険料は社会保険の保険料を決める基礎となる標準報酬月額というのがあるのですが(給料によって決まる)、退職時の標準報酬月額がそのまま適用されます。
ただし、標準報酬月額32万円以上の人は、32万円となります。
これだけ聞くと、「ん?ならお得じゃね?」と思うかもしれませんが、そんなお得でもありません。
冒頭にも記載しましたとおり、社会保険は会社が保険料の半分を負担していましたが、任意継続になると全額が自己負担となります。
なので、標準報酬月額が32万円以下の人の場合、単純に保険料が現役時代より倍になるということです。
ただ、標準報酬月額が32万円以上の人であれば、負担額が下がる可能性もあります。
いずれにしましても、退職後には、公営国保か社会保険の任意継続か、いずれかを選択することになりますが、どちらも行政に保険料推定額を確認出来ますので、お得な方を選択するのがおすすめです。
ちなみに、公営国保は市区町村役場、任意継続は協会けんぽ、又は組合健保事務所が問い合わせ先となります。
健康保険は、「病気になってから手続きすればいいや」にはなりません。国民皆保険制度といって、どこかの健康保険へ加入義務が課されていることと、2年間の遡及が法律に定められていますから、未加入期間もきっちり請求されます。
年金はどうなるのか
現在の年金制度は、国民年金と厚生年金の2種類です。公務員用の共済年金もありますが、厚生年金とほぼかわりありませんので、2種類として取り扱います。
法人の事業所や5人以上の個人事業所で働いている人は、社会保険の強制適用となりますので、厚生年金も適用されています。
退職すると、厚生年金は喪失となりますので、退職後は例え無職でも国民年金被保険者となります。
各種免除制度がありますが、今回は割愛します。
健康保険と異なり、年金制度の場合は年齢によって条件が異なります。
国民年金の加入期間は、現行制度だと60歳までとなりますので、60歳未満で退職した方は国民年金に加入する義務が発生しますが、60歳以上であれば未納期間などが過去にあって任意に加入を希望する場合を除いて、加入する必要がなくなります。
なお、退職後、社会保険適用事業所で働く、ないしは独立開業して法人事業所を立ち上げた場合には、また厚生年金に加入することになりますが、厚生年金は国民年金と異なり、現在は70歳まで加入となります。
ちなみに、2025年度の国民年金保険料は月額17,510円です。
ちなみに、年金は65歳から支給となりますので、老後の資金計画はまず65歳でいくら年金支給されるのか確認することから始まります。
毎年年金機構から送付される「年金定期便」で納付状況が確認でき、50歳以上であれば将来の年金支給予定額も記載されています。
厚労省が公的年金シミュレーターも用意していますので、一度、試してみるのも吉です。
今回は、年金給付の内容についてまでまとめませんが、現在、2階建て構造となっている年金給付の1階部分にあたる「老齢基礎年金」は40年の納付が前提となりますので、60歳前に退職するFIRE組は、国民年金加入はもちろんのこと、独立含め改めて厚生年金に加入する「年金戦略」も整理した方がいいかもしれません。
資産形成で考えると年金より投資の方が部がありますが、年金制度は老齢給付だけでなく障害年金や遺族年金など、万が一に備えた制度もありますので、投資とは別枠でしっかりと対策しておくことが大切です。
雇用保険から支給される基本手当(失業保険)
退職後、次の仕事が見つかるまで雇用保険から基本手当が支給されます。
基本手当は、雇用保険加入年数と退職理由によって給付日数が異なりますが、90~330日分支給されます。
詳細はハローワークのサイトをご確認ください。
基本手当は、退職前1年間における平均賃金の6割程度が支給されますが、上限値もありますので詳細はハローワークでご確認ください。
基本手当は、再就職する意志が前提となります。再就職できたかではなく、「意志」ですので、その「意志」を就職活動という手法で証明していけば受給できます。
なので、健康保険の項で記載したとおり「健康保険で配偶者の扶養家族加入は認めない」となるのでしょうが、なんか考え方が古いですよね。
それはさておき、基本手当の原則は上記のとおりですが、再就職活動にあたり職業訓練校などスキルを身につける教育を利用すると、給付期間が延長されることもあるようですが、その点は条件等がありますので、ハローワークでご確認ください。
いずれにしましても、せっかく雇用保険を支払ってきたのですから、退職後はしっかりと基本手当を受給しましょう。
FIREの場合、当面の生活費にもなりますしね。
その他もろもろ
退職後の主な注意すべき点は以上のとおりですが、他にも沢山あります。
- 健康診査(市区町村で実施しているので自分で情報収集が必要)
- 確定申告(収入がある場合)
- クレジットカードの発行が困難(収入がない場合)
などなどです。
逆に収入がない場合には、利用出来る制度も増えるかもしれませんので、広報はしっかりとチェックしておいた方が無難です。
まとめ
今回は、退職後に注意すべき点について、思いつく範囲でまとめてみました。
特に、住民税と健康保険料は結構な金額が必要となりますので、退職する前にきちんと当該費用を別枠で確保しておくことをおすすめします。
金額の目安は、退職前の給与明細書を確認し、天引きされている健康保険料と住民税額、そして国民年金保険料となります。
前年度所得が対象となる住民税と健康保険料(公営国保)は、1年が経過すれば今度はうんと安くなりますので、とにかく1年間の我慢ですし、別枠で確保しておく理想的な金額も1年分となります。
退職後は収入の柱がなくなりますので、こうした支出は予期しておけば大丈夫ですが、備えていないと経済的だけでなく精神的にも打撃をうけます。
しっかりと対策を講じておきましょう。
ときち



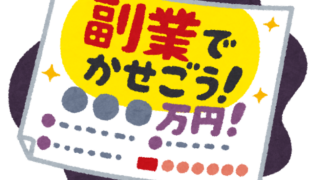





コメント