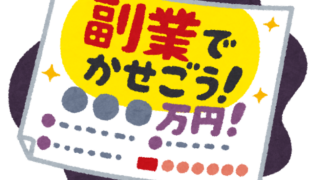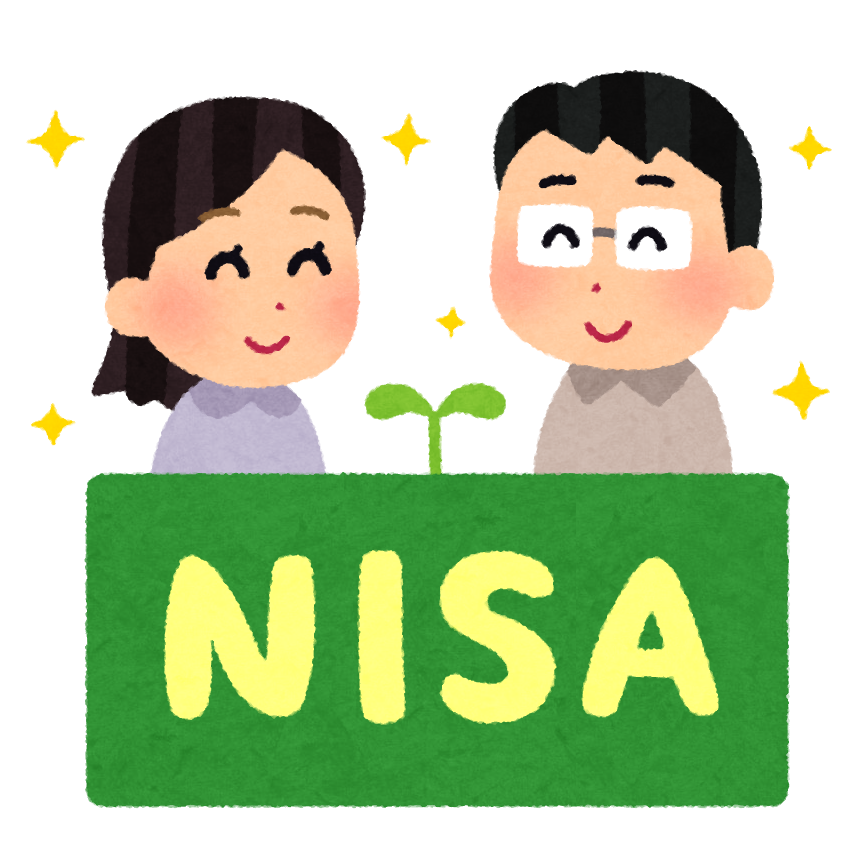50代でFIREめざしているときちです。
FIREにむけて資産形成→資産形成の柱はNISA、と書いてきたところですが、「ところでNISAってなに?」という方も多いかもしれません。妻と資産形成で話し合ったときも、「NISAって実はよくわからないんだけれども・・・」と言ってたことも思い出したもので。
そこで、今回は新NISA制度について確認します。
NISA、新NISAとは
NISA(ニーサ)とは、「少額投資非課税制度」(金融庁HPより)のことです。もともと、イギリスにISA(個人貯蓄口座)制度があるようですが、これをモデルに日本版をつくったようです。NISAは「Nippon Individual Savings Account」の略称です。
2014年1月にNISA制度がスタートしましたが、2024年から制度がかわり新NISA制度がスタートしました。かつてはジュニアNISAもありましたが、新NISAに切り替わったことにより、ジュニアNISAはなくなりました(また子どもむけのNISA制度の検討ははじまっています)。
従って、かつての制度と現在の制度を区分けするために、現在の制度は「新NISA」と呼ばれることも多いので、今回は新NISAと表現します。
旧制度から上限額などが変更となりましたが、詳しくは後ほど。なお、旧制度の口座は、新たに投資はできませんが、同制度利用開始から5年間は整理が必要です。期限までに売却して整理するか、特定口座へ移行するか、どちらかの選択となります。
NISA制度とは、「少額投資非課税制度」と記載しましたが、その名の通り投資を目的にした制度ですが、非課税で利用出来るメリットがあります。当然条件もありますが、それは制度詳細で記載します。
そもそも「非課税とは?」。投資では、分配金、配当金、売却益などの収入が見込めますが、これらには税金が発生し、現在は20.315%となります。投資で10万円の利益がでても、2万円は税金でもっていかれ、手取りは8万円になる、といったものです。
これが、NISA制度を利用すると非課税になります。ですので、投資を行うのであれば、NISA制度を利用しない手はありません。
新NISA制度の概要
では、新NISA制度の概要でが、下記の表を参照してください。
なお、表は金融庁HPからお借りしました。

保有期間や対象年齢などは表にある通りですので、解説が必要な内容に絞って記載します。
まず新NISAは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つがあります。どちらか1つしか利用できないのではなく、両方併用することができます。ときちも2つとも利用しています。
両者の違いは「投資対象商品」にあるとおりですが、実際に投資する際に、どちらに該当する商品なのかわかるようになっています。「つみたて投資枠」の方が対象商品が限定的になっていますが、「つみたて目的」なので、そうなるのは必然かと思います。なお、商品によっては、どちらにも該当するものもあります。
新NISAを利用するには、NISA口座の開設が必要です。証券会社や金融機関で利用できます。ときちは、メインバンクでNISA口座を設立し、変更手続きなどはネットで行っています。前にも記載しましたが、個別株投資は楽天証券を利用していますが、楽天証券でもNISA口座開設できます。
本当は、投資の基礎知識を身につけてからNISA口座開設が好ましいのですが、投資は長くおこなう方がいいので、新NISAをはじめる決意があるのであれば1日でもはやく始めた方がよいとは思います。ですので、基礎知識に不安がある状態で口座開設するようでしたら、メインバンクの窓口で相談した方がいいかもしれません。
なお、YouTube動画でよく「投資は窓口で相談するのはおすすめしない」と言われます。金融機関も商売ですので、金融機関に都合がよい商品をすすめてくるからです。ですので、窓口で相談する場合は、気をつけるか、口座だけ開設し、投資先は後日決める(またはネットでおこなう)など、しっかり自分で考えてから行った方がいいです。
つみたて投資枠の特徴
「つみたて投資枠」とは、その名のとおり「積立型の投資」となります。毎月、いくらを積立るのか設定し、選択した商品を購入する仕組みです。年間投資枠上限は120万円ですので、月々の上限は10万円となります(賞与利用除く)。なお、上限額を超過した分については、NISA口座の適用外となるため、特定口座となりますが、そのあたりは契約する金融機関の情報をご確認ください。
ときちは、つみたてNISA利用時は3万円からスタートし、その後、家計収支をみながら積立額を増額させ、いまは毎月9万円積み立てています。
非課税保有限度額とは、年間上限とは異なり、累計の上限額です。前項の表で記載しているとおり、「つみたて投資枠」「成長投資枠」の総額で上限1800万円となりますが、「成長投資枠」のみの上限は1200万円ですので、両方を年間上限も考慮しながら併用する場合、「つみたて投資枠」の上限額は600万円を目安に考えておいた方がいいです。
ですので、月々10万円で積み立てた場合、非課税保有限度額に到達するのは最短で5年となります。これは成長投資枠も同じです。
ときちは、定期預金も一定額利用していたのですが、定期預金の積立を新NISAへ順次移行することで、月々の積立額が9万円にまで達しました。
つみたて投資枠は、複数の商品も選択できます。ときちは、先進国投資に1万、S%P500に5万円、オールカントリーに3万円と分散していますが、1つがいいのか分散がいいのかは、人それぞれの解釈がありますので何ともいえません。投資信託利用の場合、そもそも分散投資できているので、投資信託であれば1つでもいいかもしれません。
成長投資枠の特徴
成長投資枠は、年間投資上限額が240万円です。成長投資枠は一括して購入もできますので、年当初に一括購入する人もいるようです。
ときちは、今年から成長投資枠を利用するようになりましたが、1月に120万円、3月に120万円の2回にわけて購入しました。
投資対象商品はつみたて投資枠より緩和されています。より多くの商品が利用出来ます。「成長投資枠」ですからね。目的がより「投資」の色合いが強くなっています。
非課税保有限度額は、前項でも記載したとおり1200万円となります。なので、年間上限240万円を毎年おこなった場合、最短で5年間で満額となります
なお、ときちは「成長投資枠」に関しては、オールカントリ1本に絞っています。
投資商品はNISA制度を十分活用出来るものがおすすめ
NISA制度の肝は「非課税」です。なので、非課税を最大限利用できる商品選択がおすすめです。
投資のうまみは配当金です。配当金をもらえたときは本当に嬉しいですし、配当金を利用して買い物した時、妙な罪悪感は発生しません。
しかし、NISA制度で利用するなら、配当金をもらうスタイルではなく、分配金を継続投資する商品の方がお得です。NISA制度の非課税「限度額」はあくまで元本なので、継続投資する分配金は上限額に含まれません。なのでそのまま放置しておいても、非課税枠で運用できますし、複利が利用できるので、資産形成する上でも非常にお得になります。
※投資信託で分配金を継続投資する際に、複利と呼べるのかどうか専門家でも定義に各論があるようですが、複利的な効果は望めるので、お得である点はかわりません。
ときちが利用しているのは、先ほど書いたとおりです。
まとめ
繰り返しになりますが、投資をはじめるのであればNISA制度をまずは利用することがおすすめです。ときちのように、FIREをめざし、資産形成の柱を株式投資とする方も、まずはNISA制度の利用がおすすめです。
つみたて投資枠、成長投資枠、両方を最大限利用する場合、最短で5年投資すれば上限額の1800万円に達します。ときちも、とにかく1800万円の到達をめざしていますが、このペースでいくと、最短で3年後・・・。投資は焦らずじっくり、長期投資が基本ですので、じっくりがんばります。
新NISAをはじめる場合、口座解説、投資計画(毎月いくら積み立てるのか等)、投資商品の選定、となります。特に投資商品の選定は、投資初心者にとって超難関です。旧NISAをはじめた時、金融機関担当者の説明が全く理解できず、取りあえずすすめられた商品を選択してしまったのは、よい思い出です・・・はい。
NISA制度利用前に、投資商品の情報はしっかりとおさえておきましょう。
ときち